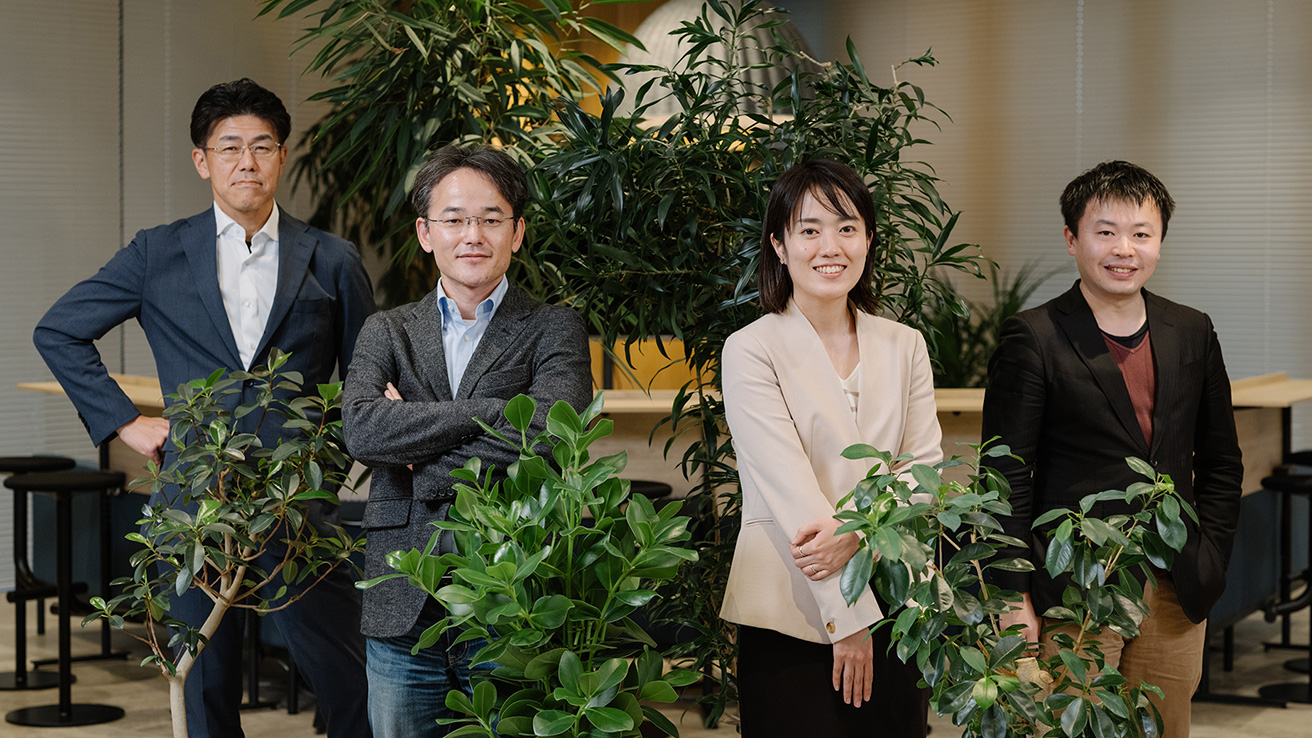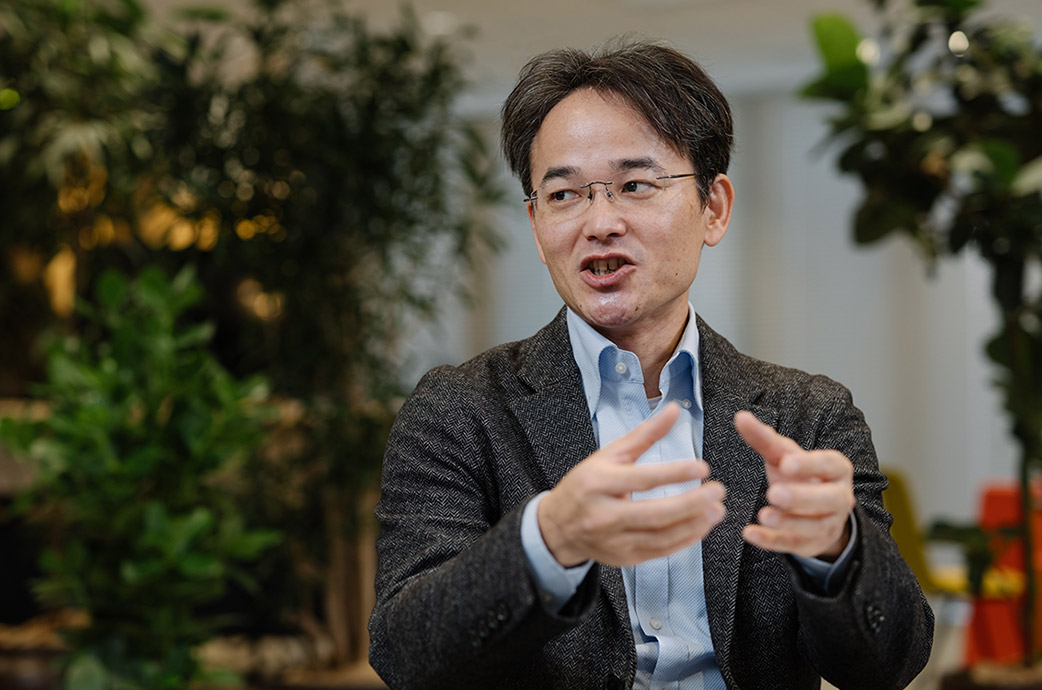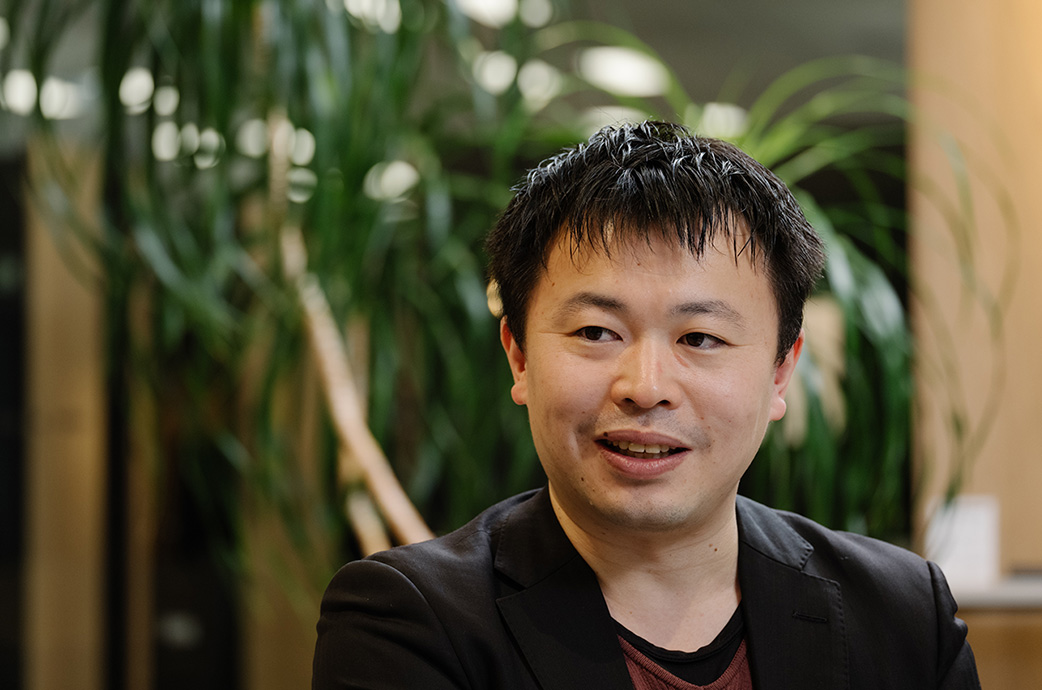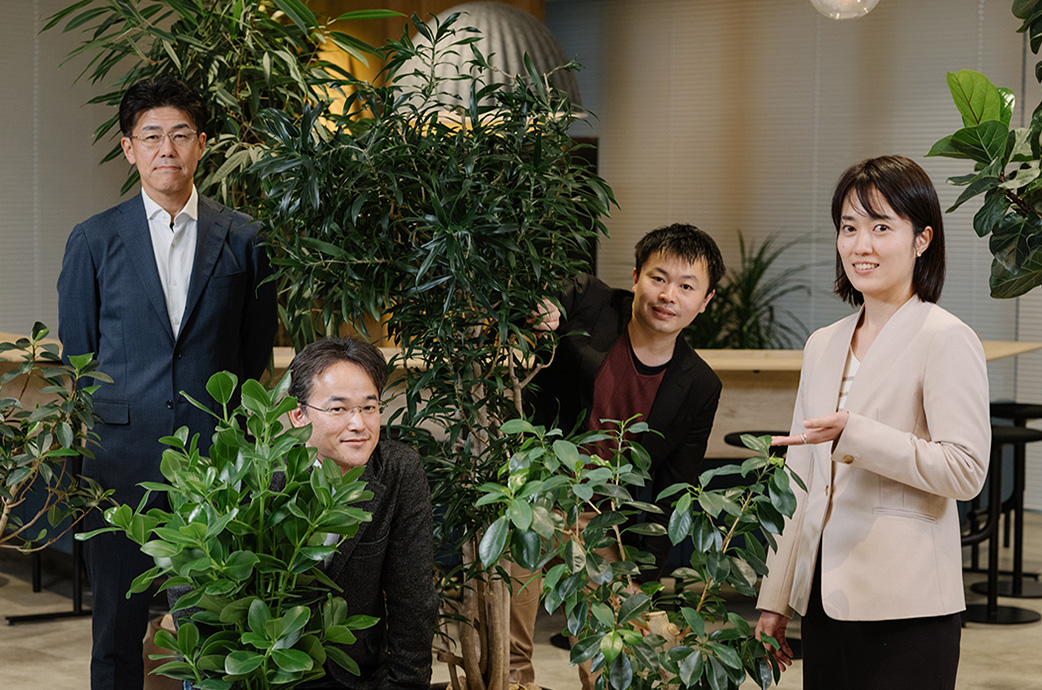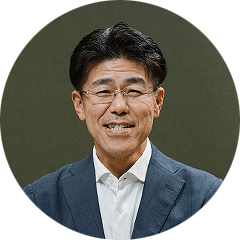下川 哲
早稲田大学政治経済学術院 准教授
北海道大学農学部農業経済学科卒業後、米国コーネル大学にて応用経済学博士号(Ph.D.)を取得。香港科技大学社会科学部助教授、アジア経済研究所研究員を経て、2016年から現職。米国の農業経済学会誌「Journal of the Agricultural & Applied Economic Association」(JAAEA)や国内学術誌「農業経済研究」などの編集委員も務める。専門は農業経済学、開発経済学、食料政策。
主な著作に、今回の対談の契機となった「食べる経済学 」(大和書房・2021年)のほか、「食から考える世界と未来 (1) ~ (10)」(日経新聞朝刊・2022年)や、「持続可能な食の実践に壁、人間の合理性の限界」(週刊東洋経済・2020年)などがある。
下川研究室公式サイト:https://prj-foodecon.w.waseda.jp/
主な著作に、今回の対談の契機となった「食べる経済学 」(大和書房・2021年)のほか、「食から考える世界と未来 (1) ~ (10)」(日経新聞朝刊・2022年)や、「持続可能な食の実践に壁、人間の合理性の限界」(週刊東洋経済・2020年)などがある。
下川研究室公式サイト:https://prj-foodecon.w.waseda.jp/