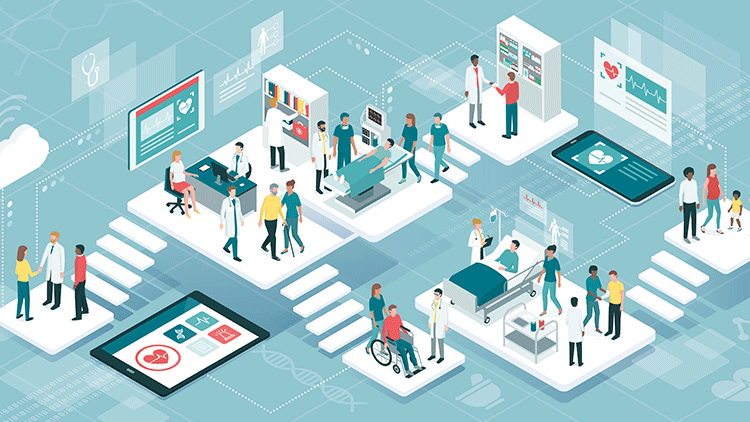国が提唱する「健康寿命の延伸」政策のもとで、日本発の医薬品・医療機器開発が期待されて久しい。身体機能を改善・補助・拡張できるロボットスーツ「HAL®」※1のように、研究者が保有するシーズの実用化に成功した事例もあるが、新規医薬品の申請を医師が行って実用化まで進むケースが増えている米国などに比べると、日本の研究開発の動きはまだ緩やかであると言わざるを得ない。
日本では医薬品・医療機器の開発を推進する臨床研究支援機関として、2015年度から、大学病院などが医療法上の「臨床研究中核病院」※2に指定されている。結果として研究者はこうした病院との間で、保有するシーズの開発戦略について相談可能になったほか、患者の協力が不可欠な臨床試験への支援を受けられるようになった。
だが、この仕組みは十分に機能していないのが実情である。臨床研究を支援する人員が欧米よりも少ないからだけではない。支援が長期的なスパンの開発戦略を欠いている点も響いている。計画書の作成や治験※3のサポートといった「入り口」段階の支援にとどまっており、保険適用の対象となって実用化にこぎ着ける「出口」を見据えるまでには至っていないのである。
研究者の側からは、それぞれの臨床研究支援機関が得意としている具体的な支援内容の違いを把握しにくくなっている。戦略面の見直しと合わせ、情報基盤を整備して各機関の支援メニューを「見える化」することで、シーズを有する研究者と、適切な支援が可能な臨床研究支援機関を「つなぐ」必要がある。
実用化に向けては資金や法的な面でのハードルも越えなければならない。このため、医療スタッフだけでなく、ベンチャーキャピタルや経営コンサルタント、弁護士、知財管理などの専門家も必要となる。臨床研究支援機関には、これら専門家への橋渡し機能も求められよう。多数の専門家が一丸となって研究者のシーズを育てるエコシステムが構築できれば、せっかくの研究成果が日の目を見ずに葬られてしまう「死の谷」を、乗り越えられるはずである。
日本では医薬品・医療機器の開発を推進する臨床研究支援機関として、2015年度から、大学病院などが医療法上の「臨床研究中核病院」※2に指定されている。結果として研究者はこうした病院との間で、保有するシーズの開発戦略について相談可能になったほか、患者の協力が不可欠な臨床試験への支援を受けられるようになった。
だが、この仕組みは十分に機能していないのが実情である。臨床研究を支援する人員が欧米よりも少ないからだけではない。支援が長期的なスパンの開発戦略を欠いている点も響いている。計画書の作成や治験※3のサポートといった「入り口」段階の支援にとどまっており、保険適用の対象となって実用化にこぎ着ける「出口」を見据えるまでには至っていないのである。
研究者の側からは、それぞれの臨床研究支援機関が得意としている具体的な支援内容の違いを把握しにくくなっている。戦略面の見直しと合わせ、情報基盤を整備して各機関の支援メニューを「見える化」することで、シーズを有する研究者と、適切な支援が可能な臨床研究支援機関を「つなぐ」必要がある。
実用化に向けては資金や法的な面でのハードルも越えなければならない。このため、医療スタッフだけでなく、ベンチャーキャピタルや経営コンサルタント、弁護士、知財管理などの専門家も必要となる。臨床研究支援機関には、これら専門家への橋渡し機能も求められよう。多数の専門家が一丸となって研究者のシーズを育てるエコシステムが構築できれば、せっかくの研究成果が日の目を見ずに葬られてしまう「死の谷」を、乗り越えられるはずである。
※1:Hybrid Assistive Limb® ; 筑波大学の山海嘉之教授らが研究開発し、同大学発のベンチャー企業で山海教授がCEOを務める「サイバーダイン社」が医療機器として製造している。
※2:2018年4月1日現在で12の研究機関が厚生労働大臣に承認されている。
※3:実地で行われる臨床研究のうち、患者の協力を得て、薬の有効性と安全性を調べることを「臨床試験」、その中でも医薬品・医療機器などの法的な承認・許可のために行われる臨床試験を「治験」と呼ぶ。
![[図]医療技術の実用化フロー](/knowledge/mreview/i6sdu6000000t1ms-img/mr201806topics3.png)