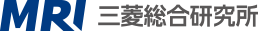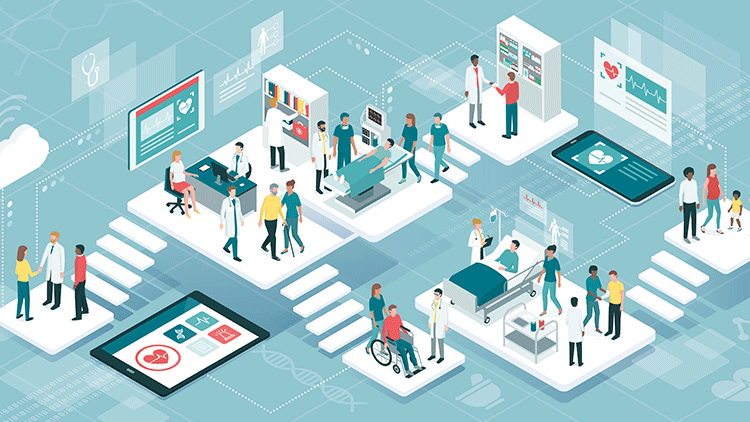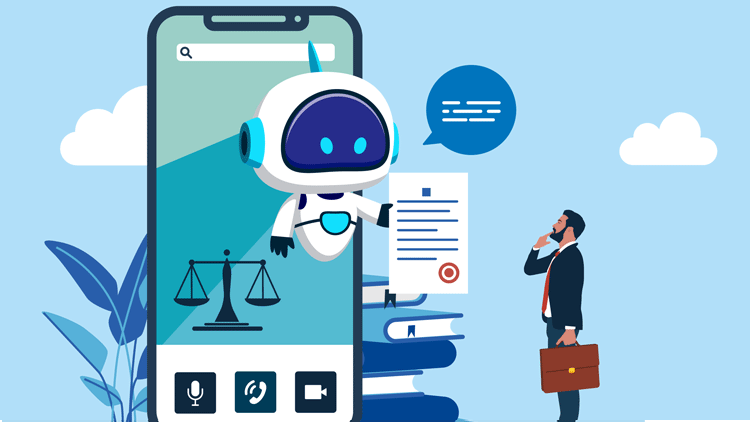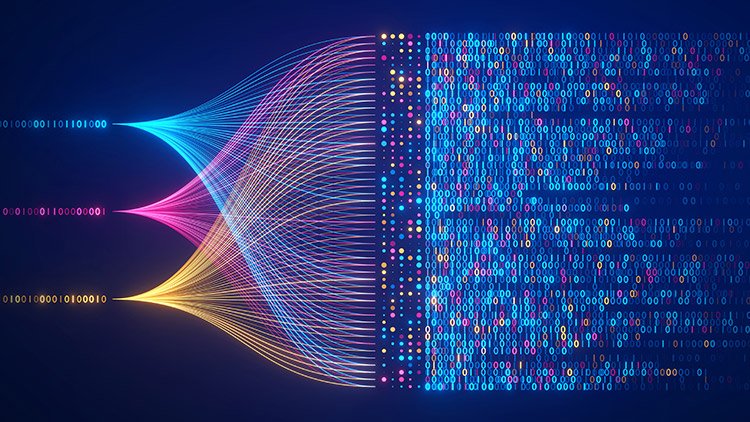外交・安全保障 第15回:有事を想定した海底ケーブルの防護・強靭化
人気の記事
タグから探す

社会・経済・防衛に欠かせない重要インフラ
海底ケーブル障害が安全保障上の重大リスクに

独自検証 台湾有事での海底ケーブル切断リスク
2023年時点で、日本には22本※9の海底ケーブルが陸揚げされており(図3)、1本が偶発的に切断されても、他の海底ケーブルにデータを迂回して通信を維持できる。しかし、複数本の海底ケーブルが同時に切断された場合、社会・経済・防衛に影響が生じると考えられる。

また、海底ケーブル切断の影響には非対称性がある。ケース3、4において日中間ケーブルが切断された場合、中国は日本との接続を失うだけであるが、日本は中国以西との高速通信が困難になる。地理的な位置関係からも、海底ケーブル切断は日本に対する効果的な攻撃手段になり得る。
官民連携がカギ 新たに取り得る4つの防護策

(1) 切断を防止する対策
A. 既存ケーブルの防護
平時では、主にケーブル船※13を保有する民間企業が既存ケーブルのメンテナンスや予防保全工事を実施している※14※15。また、今後の海洋政策の方針を定めた「第4期海洋基本計画」では、海底ケーブルの安全対策に係る政府機関として、警察庁、総務省、国土交通省が言及された※16。しかし民間企業はもちろん、警察庁や総務省も有事に防護を担う部隊を有していない。国土交通省の海上保安庁は防護部隊を有するが、非軍事組織であるため※17、有事における防護を担当できない可能性が指摘されている※18。一方、諸外国では海軍が有事に備えて、海底インフラの防護演習を実施している(表4)。日本でも、有事における海底ケーブル切断を防止するために、海上自衛隊と連携した防護体制についての議論が必要だろう。B. 新規ケーブルの防護
民間企業は新規ケーブルを海底に敷設する際に、海域の調査を行っているほか、海底面下にケーブルを埋設して物理的損傷を防ぐなど海底部の安全対策を講じている。一方で、海底ケーブルを陸揚局に接続する陸揚げ部の安全対策は相対的に脆弱性が高い。例えば、地域ごとに攻撃や破壊行為のリスクを評価し、高リスク地域への陸揚げを避けるなどの対策を講じることで、安全性が向上するだろう※19。米国では安全保障上の懸念を理由に、米中間ケーブルの陸揚げを却下した事例がある※20。日本も新規海底ケーブルの敷設を検討する際に、自国のデータを直接的に伝送する陸揚げ国を選定し、有事にも機能する通信網を構築することが望まれる。(2) 切断の影響を最小化する対策
C. 早期復旧性の確保
民間企業は要請から24時間以内にケーブル船を出動させ※14、3週間程度で損傷を修理できる※21。しかし、複数の海底ケーブルが同時に切断される有事では、ケーブル船数が不足して復旧までに追加の時間を要するだろう。これに対して米国は、ケーブル船運航者に補助金を支給することで、有事におけるケーブル船不足を解消している※22。日本でも有事に備えたケーブル船隊を編成・組織するために、船舶の建造や維持管理の費用に対して補助金を支給する施策が考えられる※23。D. 冗長性の確保
総務省は2024年に海底ケーブルの多ルート化に対する補助を実施する予定だ※24。安全保障を確保するためには、上述のように陸揚げ国を考慮しながら、できるだけ切断リスクを回避できるような多ルート化を図ることが求められる。例えば、中国の影響が比較的小さいルートとして、アラスカを介して日本と欧州を接続する北極海ルートが期待される※25(図4)。※1:総務省「情報通信白書 令和2年版」
https://www.soumu.go.jp/
※2:例えば、中・低軌道に打ち上げた多数の小型非静止衛星を連携させて一体的に運用する衛星コンステレーションの構築が進められている。
総務省「情報通信白書 令和4年版」
https://www.soumu.go.jp/
※3:慶應義塾大学 土屋大洋「日米サイバーセキュリティ協力の課題」(笹川平和記念財団「日米安全保障専門家会議」報告書⑨、2016年3月)
https://www.spf.org/
※4:「ビジネス特集 知られざる海底ケーブルの世界」(NHK、2023年6月20日)
https://www3.nhk.or.jp/
※5:ICPC, "Submarine Cable Protection and the Environment"
https://www.iscpc.org/
※6:"NATO warns Russia could target undersea pipelines and cables", POLICTICO, 2023.05.03
https://www.politico.eu/
※7:"Interview with Bloomberg" Ministry of Digital Affairs (Taiwan), 2023.05.17
https://ipfs.moda.gov.tw/
※8:"Enhancing the Resilience of Communications Network" Ministry of Digital Affairs (Taiwan), 2022.08.27
https://moda.gov.tw/
※9:日本のみに陸揚げされる国内ケーブルは集計から除いている。
※10:山崎文明氏・情報安全保障研究所首席研究員「ヤバすぎる日本の海底ケーブル 台湾有事でネット接続全滅リスク」(エコノミストOnline、2022年1月31日)
https://weekly-economist.mainichi.jp/
※11:単位時間あたりに送信できるデータの最大容量。
※12:この接続は1本の海底ケーブル(FLAG Europe-Asia)のみで確保されたものであり、通信帯域幅は約1,100Gbpsであることに留意する必要がある。この帯域幅は全帯域幅の0.1%に相当する。
※13:海底ケーブルの敷設および保守の機能を有する船舶。
※14:「海底ケーブル保守」(KDDIケーブルシップ株式会社ウェブサイト)
https://k-kcs.co.jp/
※15:「メンテナンス」(エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社ウェブサイト)
https://www.nttwem.co.jp/
※16:内閣府「海洋基本計画」(令和5年4月28日閣議決定)
https://www8.cao.go.jp/
※17:海上保安庁法第25条
※18:「誰が海底ケーブルを防護するのか 太田文雄(元防衛庁情報本部長)」(公益財団法人 国家基本問題研究所、2023年10月10日)
https://jinf.jp/
※19:他には海底ケーブルシステムで使用される機器の安全性を評価し、供給事業者を選定する対策も考えられる。
※20:"Team Telecom Recommends that the FCC Deny Pacific Light Cable Network System's Hong Kong Undersea Cable Connection to the United States" U.S. Department of Justice, June 17, 2020
https://www.justice.gov/
※21:"Under the Sea" Shipping and Marine Magazine - September 2011
https://www.iscpc.org/information/news-articles/(閲覧日:2024年4月3日)
※22:Captain Douglas R. Burnett, U.S. Navy (Retired) ”Repairing Submarine Cables Is a Wartime Necessity”, Naval Institute, October 2022
https://www.usni.org/
※23:国土交通省は「事業基盤強化計画認定制度」として、造船・舶用事業者を対象に長期・低利の融資や税軽減などの支援を実施しているが、ケーブル船の建造計画が認定された事例は報告されていない。
国土交通省「海事 認定事業基盤強化計画 一覧」
https://www.mlit.go.jp/
※24:総務省「令和5年度補正予算事業「自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業」 及び「国際海底ケーブルの多ルート化によるデジタルインフラ強靱化事業」に係る 補助金の交付決定」(2024年3月6日)
https://www.soumu.go.jp/
※25:北極海ルートは、NATOが攻撃のリスクを指摘しているロシアの近海を通過する点に留意が必要である。
※26:例えば、デンマークは同国の海域における海底ケーブルを人的攻撃および自然災害から保護し、電気通信サービスを安定供給することを目的とした、官民連携の組織(Danish Cable Protection Committee)を設立している。
Danish Cable Protection Committeeウェブサイト
https://dkcpc.dk/?lang=en(閲覧日:2024年4月24日)
トレンドのサービス・ソリューション
寄稿や講演の依頼などその他のお問い合わせにつきましても
フォームよりお問い合わせいただけます。